
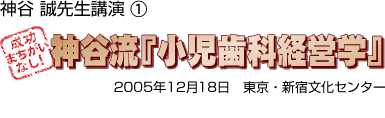

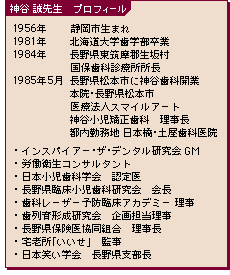
患者さんは先生のベンツ、磨いてくれますか?
私の診療目標は「患者さまを支援者に変える」です。様々な理由で医院にきてくれた患者さんと、治療を通してふれあっていくうちに「先生のところいいね」というところから「先生のところにたくさん患者さんひっぱってきますよ」とまるで選挙活動みたいに患者さんが増えていってくれるのがうれしいなと思っています。
しかし、今日はあまり難しいテーマではなく、『患者さんは先生のベンツ磨いてくれますか?』というお話です。いまだに、歯医者さんのイメージというと高級車ばっかりを乗り回しているというのがありますね。ですから、診療室の駐車場などにベンツが止まっていたりすると、「俺に入れた金歯の一部であのベンツのタイヤかなんかがあるんだろうな」というふうに思われるのでしょう。しかし、そう思われているうちは「患者さん」なのです。それが支援者になると「先生、ベンツがまだ汚れていましたから拭いておきました」となります。感謝の念から、先生にだけではなく、先生の身の回りひとつひとつに対しても患者さんが支援をしてくれる、こういうふうに患者さんが変わっていってくれたらうれしいと思うのです。残念ながら私は車にあまり興味がないというのと、レーザーおたくで、所有レーザーがこのたび9台になってしまいましたので、軽自動車に乗っております。それでも時々患者さんが入ってくると「先生フロントガラスにハトの糞が落ちていたよ」それくらい教えてくれるようになりました。深く患者さんと関わっていく中で、どう患者さんを変えていくか、その辺りの話を聞いていただきたいと思います。
私は以前、長野県の生坂村という人口3千人の小さな村の国保の診療所にいたことがあります。その時は、もう人口に比べて東西十何キロの村でしたから、村中走り回って往診したり、診療所も朝の6時くらいから夜の10時くらいまでやっていました。やっていましたというか、朝は野良作業に行く前の患者さんがいらっしゃいますし、夜は晩御飯食べて一杯飲んだ真っ赤な顔したおじちゃんたちが、なぜかしら遊びに来るので、「しょうがない、ついでだから治療してやるかな」というような診療所でした。そういったのどかな環境の中でやっているうちに、健康管理ということを、どういうふうに考えたらいいのだろうと思うようになりました。「自分の健康は自分で守ろう」というスローガンがございますが、その村の中にいますと、自分の健康を自分で守るということはなかなか難しいのです。そうすると「患者さんの健康はお医者さんが守るべき」というようなスローガンが浮かんできました。ところがそこにも限界があって、「みんなの健康はみんなで守ろう」、「地域をあげての健康作り」ということに落ち着くことになりました。それが高じて、何年か後に松本という、人口20万くらいの地方都市で、「みんなの健康をみんなで守る会」を立ち上げました。会の中で、一般の方々と医療を語り合う会として何年かやっていたことがあるのですが、いつのまにか自然消滅をしてしまいました。ただその当時からやはり医療というのは地域の中にもっと深く根付かなくてはいけないと思っておりました。特に小児歯科の部門、また在宅医療の部分ではその姿勢が必要だと思っております。

優しくて、良い先生、上手な先生
「みんなの健康作り」というテーマを、小児歯科を中心に話を発展させていきたいと思います。何年か前にマスコミにも取り上げられたことがありますが、趣味で“かぶり物”をして診療することが結構あります。「先生その“かぶり物”のヒヨコちゃんがすすけてきたから新しいのを買ってきたよ」といって患者さんから竜の“かぶり物”を貰って喜んで診療しています。多少邪魔ですが、頂き物をすると一生懸命なりきってやらないといけないので。
いずれにしても地域の中でささえられて20年になります。「小児歯科」という看板をかかげているのに、いろいろな患者さんがいらっしゃいます。日本語が全く話せない中国から来ているコックさんや、舌、口唇にピアスをしている若い方もいらっしゃいます。もうこうなってくると当院は何でもありなんだなあという思いがいたしておりましたが、その時にふと感じたのは、「なんでこういう人が当院に来るようになったんだろう」ということです。
やはり田舎のせいもあるかもしれないけれども、最近少し東京でも診療する機会があってそこでも感じているのは、「小児歯科」という看板があるなしにかかわらず、口コミ、評判として子どもを上手に診てくれる歯医者さんというのは、「良い先生」「優しい先生」だという評価があるようです。ですからうちも「小児歯科」としての診療室のあつらえをしておりますが、時々間違ってお年寄りが飛び込んでいらっしゃいます。「どうしてうちを選んだのですか」と聞くと、「なんか子ども診てくれるからすごく優しいとか思って」という答えです。そう言われると本当は気の短い私ですが優しくせざるをえない。ああそうか、子どもを診る先生は優しい先生であるべきかなと思いました。では肝心の腕の方はどうなのかというと、それはご想像におまかせいたします。
 しかし、「上手な先生」ってどこで評価されるのだろうと考えました。これは「入れ歯」が一番わかるそうなのです。私の師匠に言わせますと、「入れ歯というのは取り外し可能なんだから、良かったら入れてくれるけど、だめだったら外しちゃうんだから、はっきりわかるんだよ」。確かにそうですね。『入れ歯の上手な先生』というのはイコール『上手な先生』になるわけです。「わかった。良い先生で上手な先生だったらもうそれは最高の評価じゃないか」ということで、小児歯科でも義歯を上手に作れると無敵だな、という考えにいきついたのです。
しかし、「上手な先生」ってどこで評価されるのだろうと考えました。これは「入れ歯」が一番わかるそうなのです。私の師匠に言わせますと、「入れ歯というのは取り外し可能なんだから、良かったら入れてくれるけど、だめだったら外しちゃうんだから、はっきりわかるんだよ」。確かにそうですね。『入れ歯の上手な先生』というのはイコール『上手な先生』になるわけです。「わかった。良い先生で上手な先生だったらもうそれは最高の評価じゃないか」ということで、小児歯科でも義歯を上手に作れると無敵だな、という考えにいきついたのです。
小児患者さんにどう対応しますか?
私は大学時代に、本当に一生を変えたと言ってもいいかもしれないくらい子どもの歯科治療のきっかけをつくってくれた先生に出会いました。その先生は授業の冒頭に、これを教えてくれたのです。『毎日爪を切りなさい』。子どもを扱う場合怪我をさせてはいけない、そういう配慮なのです。2つ目は『治療中は絶対だまってはいけない。息を吐くときもそうだけど、息を吸いながらでも話し続けなさい』というような話しをしてくれました。この2つは、ある意味小児歯科の真髄かなと思いますし、私は今でもこれだけは続けております。
先生方は、いざ治療に臨んで、子どもが今にも泣きそうな時、泣いている時どのようにされますか。ものの本には『とにかくきちんと説明をして、事前にお話をしてみせて、体験をさせて、そして恐怖心をとりのぞいてあげましょう』と書いてあります。その通りだ、と私も思っておりますけれども、今にも泣きそうな時はまだなんとかなるのですが、泣いてしまっているともうしょうがないのです。説得しても何しても泣いてしまっていると聞いてもらえませんから、「しょうがないな」と言って、とりあえず座って一緒に泣くことにしています。
だいたい子どもは一緒に泣いていると半分くらいの時間で泣きやみます。「誰が泣いているんだ?」みたいな感じです。これは結構ききます。だまされたと思ってやってみてください。多分一緒に泣くのが一番早いと思っています。泣くといっても「ワー」と泣かないとだめです。一緒になって同じような泣き声でなくのです。その時に実はひとつだけやることがあります。泣くタイミングを計るのです。どういうタイミングで泣いているかな。そのタイミングを合わせていくと不思議なことに、「同じように泣いているやつがいる」と共感体験で泣く時間が短くなります。
そしてもうひとつ、泣いてふわーと吐いている時は言うことを聞いてくれないのですが、「吸っている瞬間」に、吸っている時間短いですから説得するというのはどうも無理みたいですが、この時にひとこと耳元でぼそっと言うのです。耳元で息を吸った瞬間「ウンコもれちゃうよ」と言うのです。このとき、オシッコとウンコでさんざん試してみたのですが、絶対にウンコの方がいいです。やはり糞尿期の思い出というか、その辺の原始体験があるみたいで、「ウンコもれちゃうよ」というとふっとお腹に力が入るみたいで泣きやむのが短くなります。衛生士さんにあらかじめ協力してもらうようにお願いしておきます。「ウンコもれちゃうよ」と言った瞬間に、「そうなのよ、この前先生ウンコもらしちゃったよね」と、こういうフォローを入れてもらいます。「そうなんだよ、臭かったなあ。あなたもれてない?」と、だいたいこの辺でウンコの話が盛り上がってきますから、あとは一連の話しをしながら治療が終わる所までかなりいけます。
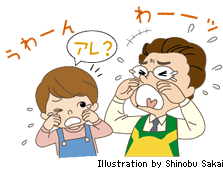 私は、小学校に入ってある程度言うことを聞いてくれてお口を開けていられるお子さんでも、だいたい連続3分から5分位が限界かなと思っています。大人は治療中は口を開けても鼻で息をする。当たり前のことです。最近はできない人もいますが。ましてや子どもは治療をうけて口の中に刺激があると、鼻でうまく呼吸することが出来ないことも多いのです。それを教えることは教えますが、難しい。そうすると口だけで息をしているとどうしても治療は大変です。特にうちでは殆ど必要がないくらいでもラバーダムをして治療をしますので、あまり長い時間やっていると疲れてしまうので、3分から5分くらいを目安にしています。その位の時間でしたら、先生方も『ウンコネタ』というのを作っておけると思います。そこには衛生士さんとの呼吸が大切です。先生ひとりがウンコの話をしていると、なんか最後はすごい汚いものを見るような目で見られてしまいますが、衛生士さんとふたりだと「わーここは楽しいな」という雰囲気が作れます。
私は、小学校に入ってある程度言うことを聞いてくれてお口を開けていられるお子さんでも、だいたい連続3分から5分位が限界かなと思っています。大人は治療中は口を開けても鼻で息をする。当たり前のことです。最近はできない人もいますが。ましてや子どもは治療をうけて口の中に刺激があると、鼻でうまく呼吸することが出来ないことも多いのです。それを教えることは教えますが、難しい。そうすると口だけで息をしているとどうしても治療は大変です。特にうちでは殆ど必要がないくらいでもラバーダムをして治療をしますので、あまり長い時間やっていると疲れてしまうので、3分から5分くらいを目安にしています。その位の時間でしたら、先生方も『ウンコネタ』というのを作っておけると思います。そこには衛生士さんとの呼吸が大切です。先生ひとりがウンコの話をしていると、なんか最後はすごい汚いものを見るような目で見られてしまいますが、衛生士さんとふたりだと「わーここは楽しいな」という雰囲気が作れます。
神谷流“口コミ”操作術『ゆりかごと墓場だけ』
『ゆりかごから墓場まで』という言葉には、まさしくホームドクターとか主治医などという意味があるかと思うのですが、私はあえて『ゆりかごと墓場だけ』と、スタッフに訓示をいたしました。とにかく生まれてまもない赤ちゃんから、子どもたちの成長を見守って、あとは義歯の方々を重点的にやっていこう。そこが上手にできたら『良い先生』で『上手な先生』なのだから、真ん中の年齢層、大多数の部分は自然に評判もついてくるだろうし、悪い影響は与えない。とにかくここを重点的にやろうと神谷歯科では考えております。
しかし、なかなか歯科というのは話題にのぼらない。患者さんが来ない。神田昌典さんという有名なコンサルタントの話で、口コミによる宣伝というか営業というのが一番確実だし確かだというのがあったような気がします。ですから人から人へと口に伝わって評判を呼ぶためには、人の話題にのぼらなくてはいけなのです。でも歯科は話題にのぼらないです。のぼったとしても「あそこで100万取られちゃったよ」など悪い話です。「あそこの先生逃げちゃったよ」なんていうのもよく聞きますし、そういう話は多くあるのですが、「素晴らしい先生だ」という話はあまり聞かない。なぜ話題にのぼらないのか。痛くなると「どこかいいところない?」と人に頼って聞く場面は結構あるのですが、そのお母さんがひとたび買い物にいってお母さん同士が井戸端会議のようにしていても、どうも話題にのぼらない。これはどうも考えてみると、歯科というのは自分の恥をさらすようなもので、「あの先生いいのよ、すごい上手な治療だったよ」と言うと「あなたむし歯だったの」とかえってきて、自分の弱点をさらすようなことにもなりかねない、つっこまれるとなんかどうもいやだわみたいに、あまり話題にのせたいというようにはならない気がします。
でも、ゆりかごと墓場は違うのです。口コミ操作ができるのです。まずは、私たちは歯の治療、これに終始するだけではなくて、子育てに深く関わっていけばいいのです。子育ての話題にはつきないものですから。公園デビューしているお母さんたち、「おたくの子どこの塾にいっている」とか、「どんなお洋服を着せている」とか、そのような話しの中で、子育ての一環として、「歯を治したらうちの子は成績があがったのよ」ということでもあれば話題にのぼらないわけがない。我が子かわいいお母さんを歯援(しえん)して、そういうところに私たちもくいこんでいけばいいと、これが歯科における口コミ操作のまず一番大きなポイントではないかと思っております。
もうひとつ『墓場』の方ですが、お年寄りが寄り合い場に行くと、やはり食べることが楽しみなものですから「私はこのたくあんは硬くて食えない」とぼやいた時に、向いにいるじいちゃんがパッと取ってパリパリと食べたりすると「あなたいい歯しているね」と、いやおうなしに話題にのぼるでしょう。やはり問題は中間世代の人たちがいかに歯科を話題にして普段の生活の中で話しをしてくれるか、これはいまだに私も悩んでいます。先生方でもし、そんなところで口コミ操作のポイントをご存知の方、実践していらっしゃる方がいたらぜひ教えて下さい。広告とか電話帳とか近隣を営業するとか、人脈作りをするとか、色々ありますが、まずは話題にのぼるような、そんなところに食い込んでいこうというのが私が考えている口コミ操作術の最大のポイントであります。