
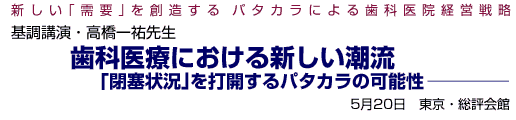
本日は三社祭りで熱気に溢れていますが、私どもの歯科界の現状は、残念ながら閉塞状況だと思います。今日参加された先生方には、ぜひ熱気あふれる歯科医療を展開していただきたいと思っております。
「局所的外科的」な近代の歯科医療
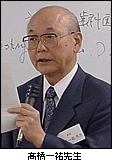
私は、パタカラに見られる歯科医療の新しい潮流ということについてお話しいたします。その前に現状の歯科医療の前、つまり近代歯科医療というものがどのようなものであったのかということをご説明しなければなりません。いろいろな考え方がありますが、我々の歯科医療はふたつのジャンルに統括できます。一つは外科的な歯科医療です。保存や矯正は、実はこの外科的歯科医療に属しています。保存学がどういう形で表現されているかというと、窩洞形成、窩洞分類。それを分類したブラック先生の膨大な著書の中で、窩洞の分類はわずか1〜2ページしか記述されていません。そのほとんどは、歯科医学全般について記述され、病理学から疫学まで全部書いてある。つまり歯科医学とは Operation、即ち Operative Dentistry といわれたのです。保存も「外科的」、当然 Endodontics、抜髄や歯根切断などはオペレーションです。それからPerio。歯周疾患に対するスケーリングや様々な処置も実は Operation なのです。そういうものが一切包括されております。それから矯正、Orthodontics も実は外科的処置に属します。もちろん手術・抜歯を含む Oralsurgery。このように、私どもの歯科医療は全て「外科的な医療」に包括されます。そしてもうひとつ全く違うもの、それが補綴学的処置、Prosthetic Dentistry であり、近代歯科医療はこのように研究され、教育されてきているわけであります。
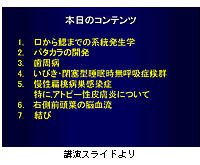
「局所から全身へ」の新しい潮流
ところが、近年研究が進むにつれて、歯科医療の考え方が、このような局所的な問題から全身的なものの考え方に少しずつシフトされてきています。そのひとつの大きな流れが「咬合」です。それも単なる咀嚼ではなく、咬合と全身との関係として、局所から全身へという展開が、20世紀の後半から学問的な流れとなってきました。今、活発に活動している「全身咬合学会」などのように、歯科と医科との関連が非常に密になり、一緒に研究や臨床をやるという時代に変化してきています。ご存知のように、腰痛や肩こり、頭痛、ストレス、それから不定愁訴、あるいは脊髄との関連などが学会等でひろく論議されております。
全身と咬合との関連のほかにもう一つ発達しているのが筋肉(Muscles)、筋機能と全身との関係です。これは20年程前からいろいろ研究されていますが、主として咀嚼筋が対象でした。これは、おもに咀嚼筋と咬合、つまり咬筋や側頭筋などのデータを分析し、筋電図などを使って咀嚼の問題として扱ってきました。
 しかし、パタカラは全く違います。これは実は誰もわからず、注目もしていなかった口唇を中心とした表情筋の役割を明らかにしました。表情筋ですから、笑いや表情を表すだけだと思われていたのですが、この筋肉の活躍が、実はすごいところに影響があることが、光ポトグラフィーという脳波の研究の結果わかってきました。嚥下や咀嚼には前頭葉の右側の血流が一番問題になり、それには咀嚼筋が一番大きく影響していると思われていたのですが、実はそれ以上に、口唇の動きが非常に大きな関係があるということがわかってきたのです。
しかし、パタカラは全く違います。これは実は誰もわからず、注目もしていなかった口唇を中心とした表情筋の役割を明らかにしました。表情筋ですから、笑いや表情を表すだけだと思われていたのですが、この筋肉の活躍が、実はすごいところに影響があることが、光ポトグラフィーという脳波の研究の結果わかってきました。嚥下や咀嚼には前頭葉の右側の血流が一番問題になり、それには咀嚼筋が一番大きく影響していると思われていたのですが、実はそれ以上に、口唇の動きが非常に大きな関係があるということがわかってきたのです。
それは、摂食の問題にも関係してきます。それから音をつくる「構音」にもこの辺の筋肉が非常に影響してきます。あるいは睡眠時の無呼吸やいびきなどにも関係してくる。アトピーや皮膚疾患、さらにいろいろな手法を試みますと、歯周病にも非常にいい結果が得られるというところまで進んできております。
近代医療の「成熟と限界」
学問・研究の進歩とともに、表情筋のトレーニングというものを、特殊な状況ではなく、我々が日常的に実施すべきだというふうに変わってきているのです。そこに非常に大きな意義があります。それを含めて私は「歯科医療の新しい潮流」と言っているのです。もうひとつ、その潮流の背景には、実は我々が大学で習ってきた「近代医療」の「成熟と限界」ということがあげられます。その「限界」の論議が近年大変活発になって参りました。近代医療の成熟とは、端的に申しますと先端技術の発達です。これはご存知のように遺伝子の構造や機能の解明がすすみ、病気にしても、非常に深いところまで分析や解析が進んでいます。近代医療イコール分析科学です。それは、ゲノムのように極限まで進んで、例えば東京ドームの中のゴルフボール1個という次元の話になる。しかし、そこに近代医療の限界があるのです。歯の脱灰・石灰化の問題にしても、近代の分析科学と実際の臨床の間には大きなギャップが存在しています。
 そういう部分的な「局所」から「全体」「全身のなかで」という考え方に進んでいますから、こんどは医療が個人の資質、つまりこの人はどのような遺伝子を持ち、資質を持っているのかということから、その資質に合わせた全身的な対応をしていくことになってゆきます。歯科医療も、一本一本の治療ももちろん大切ですが、私は、それにプラスして全体的な発想がないとこれからの歯科医療は落ちこぼれになってしまうと分析し、危惧しております。この中には東洋医療的な考え方も入ってきます。「全身的なもの」には心のケアまで入っていかざるをえない状況です。これは非常に難しいことですが、ある程度クリアしなければならない課題です。
そういう部分的な「局所」から「全体」「全身のなかで」という考え方に進んでいますから、こんどは医療が個人の資質、つまりこの人はどのような遺伝子を持ち、資質を持っているのかということから、その資質に合わせた全身的な対応をしていくことになってゆきます。歯科医療も、一本一本の治療ももちろん大切ですが、私は、それにプラスして全体的な発想がないとこれからの歯科医療は落ちこぼれになってしまうと分析し、危惧しております。この中には東洋医療的な考え方も入ってきます。「全身的なもの」には心のケアまで入っていかざるをえない状況です。これは非常に難しいことですが、ある程度クリアしなければならない課題です。
パタカラで歯科医療の活性化を
こういうものを統合して、アメリカでは今 Complementary and Alternative Medicine (相補代替医療)ということがいわれております。(私は Medicineから Dentistry にしていきたいと思っています)。これは統合(Total)という意味ですが、この中には、もうひとつ Traditional(伝統医療)も含まれています。例えば、つぼ療法などは伝統医療に属しますが、このように近代医療だけではだめだということが、いまアメリカで大きく注目されています。まさにパタカラはそこを衝いているものなのです。今、アメリカでは相補代替医療がすごい勢いで浸透しています。例えばNIH(国立衛生研究所)では、近代医療が限界にきているから、様々な対象、例えば健康食品、そういうところまで研究しろということで、各大学に2000万ドルも研究費を出しています。2000万ドルは日本円で250億です。例えばこれを日本の29の歯科大・学部に分配すると、8億円くらいになります。日本では私も以前、文部省の科学研究費120万をもらうのに大変四苦八苦した経験があります。アメリカがすごいのはこういうところにある。そのくらいの規模の中で、近代医療の成熟と限界のなかで新しい医療を推進すべく努力しています。ですから私も、こちらの研究も進めてNIHにレポートを提出して「どうだ」というくらいの意気込みは持っております。そのくらい、パタカラには潮流を変える要素があるのではないかと思っているのです。
ぜひ先生方には、パタカラによる熱気あふれる歯科医療を展開していただきたいと願っております。
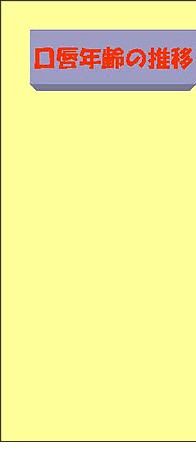 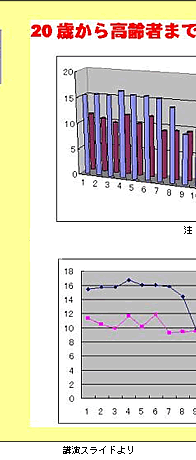 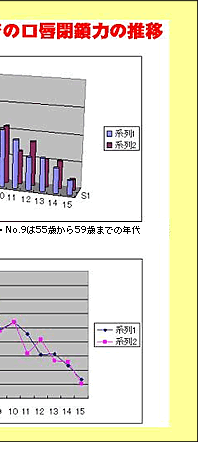 |